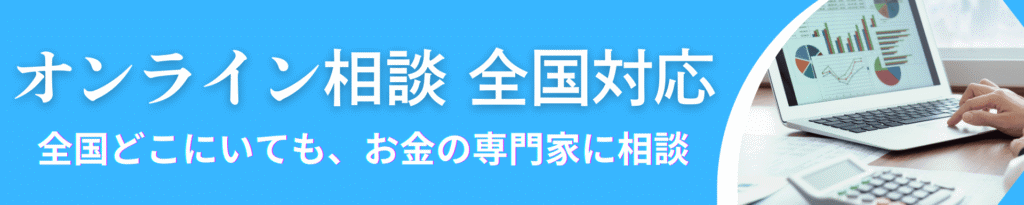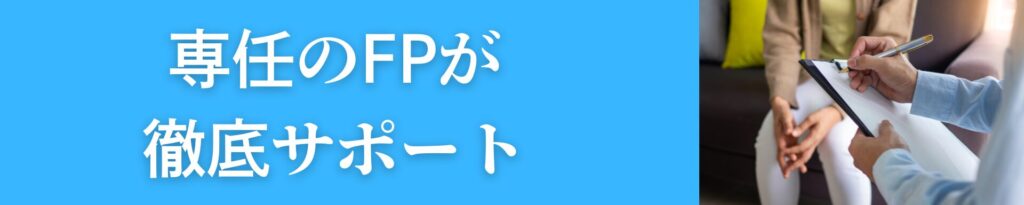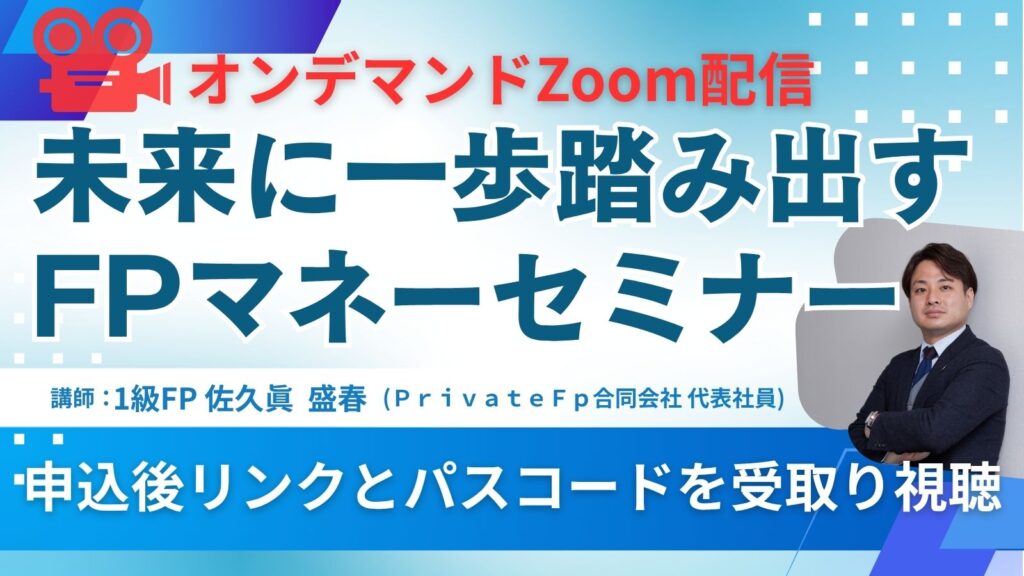【1級FP監修】NISA、iDeCoで亡くなったら?相続時の手続きや税務を解説や比較

NISAやiDeCoが身近になり、両制度を資産運用で利用する方が増えています。
しかし、利用者が亡くなった後のお手続きや税などは以外にも知られていません。
利用者は、将来に必ず起こる死亡時を想定する必要があります。
NISAやiDeCoで運用中の本人や家族が知っておく相続時のお手続きや違いを解説します。
目次
【結論】iDeCo、NISAの死亡時の相続手続き、税務上の取扱いは全く違う、家族に事前に説明しましょう。
NISAの場合、他の金融資産と一緒のお手続き
相続時手続き
NISA利用者が亡くなったら開設している金融機関に届け、相続の手続きを開始します。
金融機関によって株式や投資信託などを相続する代表者に一括して移管する場合や遺言などで誰に、何を、いくら移管するか細かく手続きできる場合もあります。
株や投資信託を移管する相続人(財産をもらう人)のNISA口座に移すことはできず、課税口座に株や投資信託の有価証券のまま移管されます。
相続人に移管される有価証券は被相続人(亡くなった人)と同じ金融機関の証券口座の移管であること条の件が多いです。被相続人と同じ金融機関の証券口座を開設する必要があります。
税金
NISA口座で保有している株や投資信託は相続税の対象となります。
相続税は相続財産の総額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)を差し引くなどして求められます。また、相続人が移管後の株式や投資信託の取得価格は被相続人(亡くなった人)の取得価格を引き継がず、個人が死亡した日の終値が取得価格なります。※課税口座の有価証券を移管した場合は有価証券の取得価格は引き継がれます。
iDeCoの場合、供託される場合も
相続時の手続き
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者・運用指図者の方が亡くなられた場合、ご遺族の方が死亡一時金を受給・請求することができます。
NISAや他の有価証券と違う所は確定拠出年金法により受取人の順位が定められており、最も上の順位の方にのみ請求する権利があります。亡くなられた方が生前に受取人を指定していた場合は指定されていた方が優先されます。
iDeCoも申込んだ金融機関(運営管理機関)に加入者等死亡届や死亡診断書などを提出・手続きする必要があります。iDeCoで運用する有価証券は投資信託のまま移管できず、金融機関が解約するタイミングの運用実績に応じて現金で一括支払いされます。
死亡日から5年を経過すると相続財産の扱いとなり、相続財産の扱いとなった後もご請求がない場合は法務局に供託されます。その後、請求の時効を過ぎると国庫に帰属されます。
税金
「死亡一時金」の支給が確定した日が死亡日から3年以内とそれ以上では適用される税法が異なります。
3年以内の場合、遺族が一括で受取れる死亡一時金はみなし相続財産として相続税の対象となります。みなし相続財産として、税法上死亡退職金と同じ扱いで法定相続人×500万円まで非課税があります。
死亡保険金の非課税とは別枠になります。
亡くなられてから3年を超えて支給されることが確定したiDeCoの死亡一時金は受け取った相続人の一時所得です。
相続手続きの流れや主な違いの比較表
| 項目 | NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 投資益の非課税(運用支援) | 老後資金の自助努力(拠出控除+運用益非課税) |
| 相続発生時の基本形 | 非課税は死亡日までで終了 | 死亡一時金として支給(原則現金一括) |
| 受け取り形態 | 保有有価証券は課税口座へ相続移管(相続人のNISAに引継ぎは不可) | 受取人の順位に従い現金で支給(運用成果反映) |
| 税の扱い(原則) | 相続税の対象(評価は死亡日の終値等)→以降の譲渡益等は課税 | 3年以内確定=相続税(退職手当金等非課税:500万円×法定相続人)/3–5年=一時所得/5年超=相続財産扱い |
| 手続きの流れ | 相続税の評価・申告(死亡日の終値等で評価) 取引金融機関へ死亡の連絡 相続人代表を決定 必要書類提出(戸籍・相続関係書類 等) 有価証券を課税口座へ移管(相続人側で口座要件に注意) | 税区分:3年以内=相続税/3–5年=一時所得。 運営管理機関へ届出(加入者等死亡届・死亡診断書 等) 受取順位の確認(指定があれば優先) 死亡一時金の請求(原則現金一括) 期限管理:5年以内に請求、超えると相続財産扱い→未請求は供託へ |
| 主な必要書類 | 死亡届・戸籍関係・相続関係説明図 等 | 加入者等死亡届・死亡診断書(写)・受取人確認書類 等 |
| 評価基準日 | 死亡日(保有商品の時価等) | 原則、請求に基づく支給額(運用成果反映) |
| 請求・期限 | 金融機関の指示に従い相続手続き | 5年以内に請求(未請求・受取困難で供託の可能性) |
| 受取人の決まり | 相続人(遺言・法定相続) | 指定があれば指定受取人が優先→なければ法定順位 |
| 注意点 | NISA枠は承継不可/手続き中の売買・出金制限に注意 | 期限超過・受取人不在など実務上の滞留に注意 |
| よくある誤解 | 「相続人のNISAにそのまま移せる」→不可 | 「いつでも相続税」→経過年数で税区分が変動 |
| 相談先 | NISA口座保有の金融機関 | 運営管理機関 |
※上表は一般的な取り扱いです。具体の税務判断は所轄税務署・税理士へご確認ください。法令・運用は変更されることがあります。
家族に共有
NISAやiDeCoは資産形成において有益な制度ですが、万が一の死亡時の手続きや税金の扱いなど本人や家族が把握する必要があります。
日頃から家族のコミュニケーションを大切にして、生涯や世代を超える資産運用に取り組んでいきましょう。
PrivateFpは数多くの金融資産運用設計の経験から、家計に合った資産運用を支援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
【関連記事】SBI証券、楽天証券iDeCoへ引っ越し、運営管理機関の変更
Q&A よくある質問
-
NISA保有者が死亡したら非課税は続きますか?
-
非課税は死亡日までです。その後は有価証券のまま課税口座へ移管されます。
-
iDeCoはいつまでに請求すべき?
-
5年以内に請求しましょう。超えると相続財産扱い→供託の可能性があります。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
公式サイト iDeCoホームページ
公式サイト 国税庁ホームページ No.4105 相続税がかかる財産
お問い合わせ
LINE相談受付中
↓FP商品広告↓
FP節約できる広告