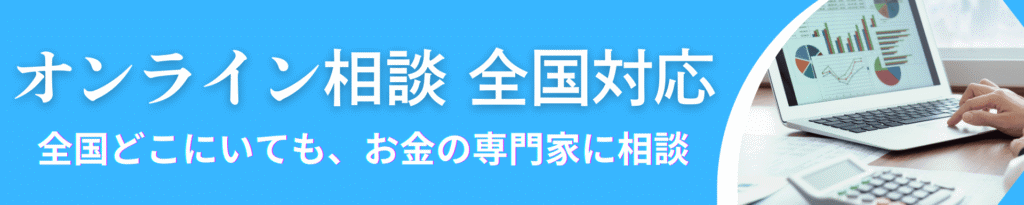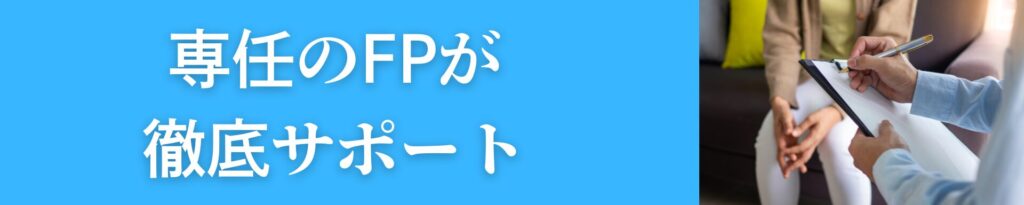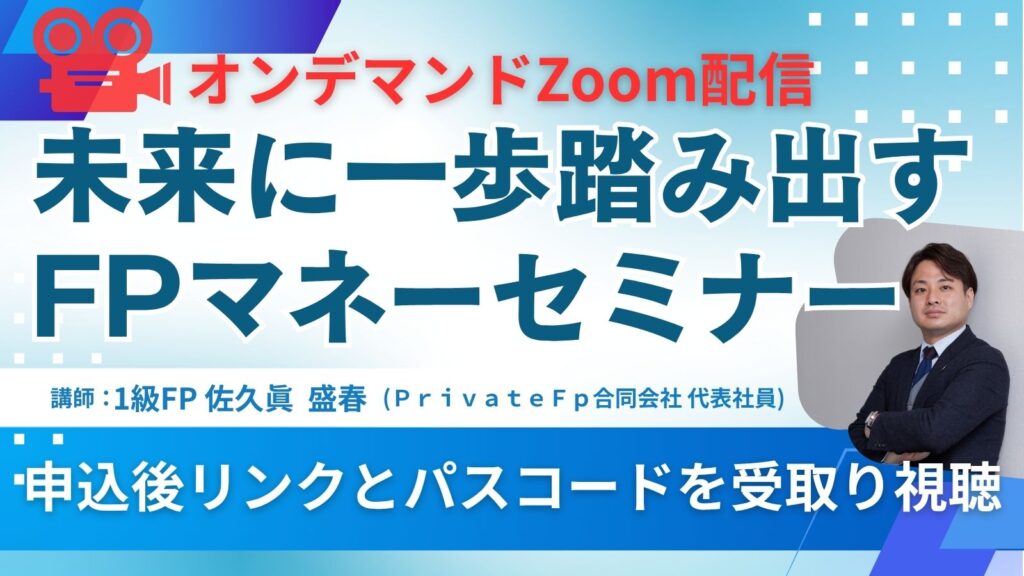【1級FP監修】不動産売却などの譲渡に係る税金や特別控除を解説

不動産(土地・建物)を売ると、利益部分に譲渡所得として所得税・住民税が課されます。
譲渡所得は給与等に掛る給与所得、年金等に掛る雑所得などと合算する総合課税の譲渡所得と分離して計算する分離課税の区分がありますが、土地や建物あるいは株式等を譲渡所得は分離課税になります。
普段の生活では馴染みのない不動産の譲渡所得ですが、マイホームの住み替えや実家の売却、相続した不動産を売却するケースで発生します。
意外と身近に発生する譲渡所得に係る税金や特別控除を解説します。
目次
【結論】譲渡所得の計算方法や特別控除を把握して、焦らず・賢く不動産を売却しましょう。
譲渡所得の計算式
基本となる計算式は次のとおりです。
譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除
- 取得費:購入代金、仲介手数料、登記費用、登録免許税、不動産取得税、増改築等の資本的支出や所有権などを確保するために要した訴訟費用も含まれます。建物は減価償却を差し引いた金額になります。取得費が不明な場合は、概算取得費(譲渡価額の5%)を取得費とすることができます。
概算取得費が判明している実際の取得費より多い時も概算取得費を選択できます。
土地・建物の取得費を土地は実際の取得費、建物は概算取得費などと分けて選択することも可能です。
また、相続や贈与で取得した不動産は取得費を引き継ぎます。※限定承認の相続及び包括遺贈を除く。
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費・解体費(用途・要件による)、立退料、抵当権抹消費用、契約書の印紙税、借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料などです。
分離課税の税率は所有期間で区分(短期/長期)
判定は譲渡年の1月1日現在の所有期間で行います。
原則の税率は次のとおりです。
5年以下(短期譲渡所得):所得税等 30.63%+住民税 9% = 合計39.63%
5年超(長期譲渡所得):所得税等 15.315%+住民税 5% = 合計20.315%
相続や贈与で取得した場合は、原則被相続人等の取得日を引き継ぎます。
ポイント:所有期間と居住用特例の有無で税額が大きく変わる。売る前に要件を必ず確認しましょう。
居住用で使える主な「特別控除」と軽減
3-1. 居住用財産の3,000万円特別控除
自宅(居住の用に供していた家屋と敷地)を売ったとき、一定要件を満たせば最大3,000万円を譲渡所得から控除できます。
居住用財産の所有期間はこの特例の要件ではありません。ただし、3年に1度しか適用できません。また、直系血族族間売買、配偶者への譲渡や特殊関にある法人などは対象外です。住まなくなってから売る場合は期限要件3年経過後の年末12月31日まで譲渡する必要があります。
3-2. 10年超所有の軽減税率(居住用)
譲渡した年の1月1日において10年超所有し売却した居住用財産である土地・建物の譲渡した場合、3,000万円控除後の課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に所得税等10.21%+住民税4%=合計14.21%が適用されます。6,000万円超部分は通常の長期譲渡所得の税率(20.315%)です。
上記の居住用財産の3,000万円特別控除と重複適用できますが、下記の空き家に係る3,000万円特別控除には重複適用できません。
3-3. 空き家に係る3,000万円特別控除
一定の「相続した空き家」(旧耐震の戸建等)を耐震改修または解体した上で売却すると、要件・上限・期限付きで最大3,000万円控除できます。売却価格が1億円以下、1981年5月31日以前に建築された家屋、自治体の確認などの細かい条件が多いため実務では事前確認が必須です。
【関連記事】空き家に係る譲渡所得の特例の改正(見直し・延長)税金対策
3-4. 公共事業の収用等の5,000万円特別控除
公共事業による収用・買収・移転等の場合、手続に沿えば最大5,000万円控除できます。収用等の証明書の保管、最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていることなどが要件を確認しましょう。
3-5. 譲渡損失の通算・繰越
自宅などの主たる居住用財産の売却で損失が出た場合、一定条件で給与等との損益通算や3年繰越控除が可能な制度です。
譲渡する居住用財産のローン要件や新居取得・ローン要件などの細かい条件が多いため実務では事前確認が必須です
不動産譲渡のよくある落とし穴、失敗の実例
減価償却の失念:建物の取得費は償却後で計算しましょう。結果として課税所得が増えることがあります。
概算取得費の乱用:概算取得費は5%です。当時の売買契約書、領収書など実額の証憑が揃えば、税負担が減ります。
確定申告:課税譲渡所得(利益)があれば原則として翌年の確定申告が必要です。売却損でも損益通算などの特例を使うなら確定申告をします。
親族・同族会社への低額譲渡:みなし贈与課税の心配があります。時価妥当性の担保(評価根拠)が必要です。
居住実態の証明不足:住民票異動だけでなく、郵便物・公共料金の宛先、通学区・ETC利用など実態資料を揃えましょう。
消費税の取り扱い:土地には消費税が課税されません。建物については、売り主の属性により消費税が発生する場合があります。
期限ミス:相続空き家・収用等は期限があります。事前の情報収集と売却時期の設計が重要です。
賢く不動産の譲渡を行う
不動産譲渡の税務は、所有期間の判定、取得費と譲渡費用の精査、特別控除の適用設計が三本柱になります。
売却前に条件を洗い出し、手取り最大化と納税額の間違いなど申告リスク低減を両立させましょう。
制度は改正・期限延長等があり得るため、実行前に最新の公的資料のアップデートと税理士や不動産譲渡に詳しいFPと確認するのが安心です。
PrivateFpは数多くのファイナンシャル・プランニングの経験から、あなたに合った上手な不動産運用設計、売却後の資産運用設計を支援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
Q&A よくある質問
-
3,000万円特別控除と10年超軽減税率は併用できますか?
-
居住用の3,000万円特別控除と10年超軽減は併用可です(空き家特例とは併用不可)。
-
取得費が不明な場合は?
-
概算取得費(譲渡価額の5%)を使えますが、実額の方が有利なことも。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
公式サイト 国税庁ホームページ No.3202 譲渡所得の計算にしかた(分離課税)
公式サイト 国税庁ホームページ No.3302 マイホームを売った時の特例
お問い合わせ
LINE相談受付中
↓FP商品広告↓
FP節約できる広告