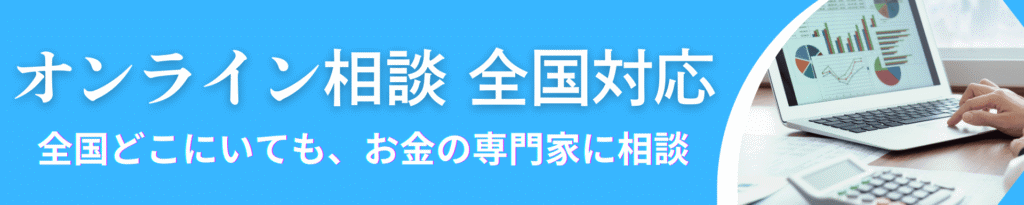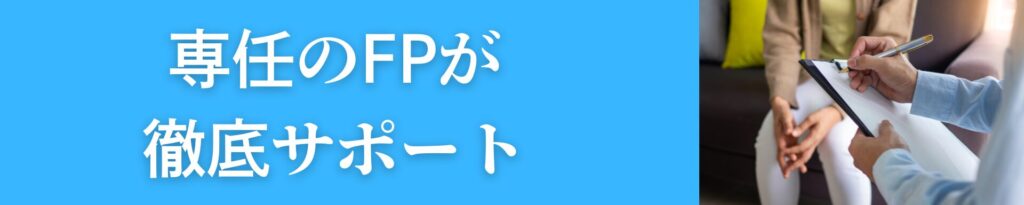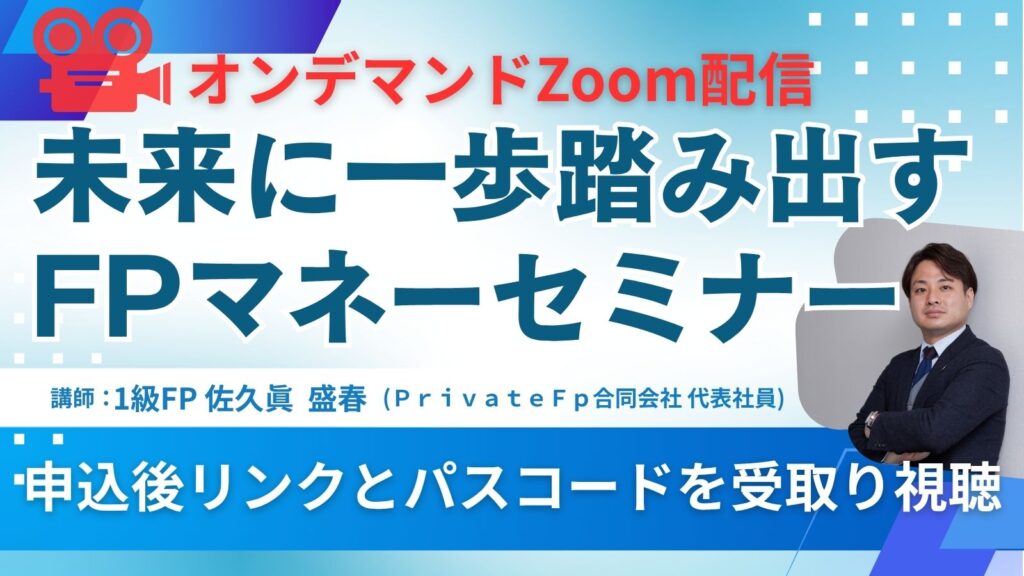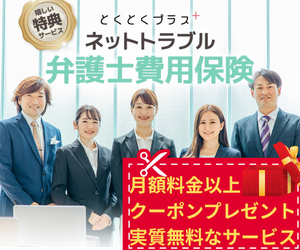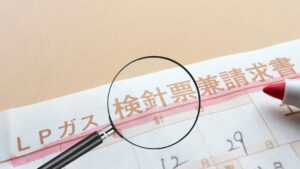【1級FP監修】年末調整の書き方ガイド、必要書類と書き方のポイントを解説

「年末調整の書類、毎年なんとなく書いているけれど、正直よくわからない…」、「パソコンやスマホ入力に変わってから余計に不安…」そう感じている方はとても多いです。
年末調整は、給与から天引きされてきた所得税と、本来の税額との差額を精算する大事な手続きです。
今回は「年末調整 書き方」「年末調整 必要書類」「もし忘れたら」といったキーワードでお悩みの方に向けて、
- 年末調整の基本
- 書き方・入力の流れ
- 生命保険料控除など、見落としやすいポイントなどを
FPの視点からわかりやすく整理しました。
会社員やパートで働く方、そのご家族の方も、はじめてでも迷わず年末調整ができるようにポイントを解説します。
目次
【結論】家族の年収や生年月日を把握、各種所得控除を利用する。控除を忘れたら還付申告を行いましょう。
年末調整とは?まずは全体像を押さえよう
年末調整とは、1年間の給与所得について、本来支払うべき所得税を計算し直し、払い過ぎ・払い足りない分を精算する手続きです。
- 給与を支払う企業は毎月の給料やボーナスからは、概算で所得税が天引きして所得税を納めています。
- 年末に、扶養家族の状況や保険料控除などの各種控除の情報を会社に申告することで、正しい所得税額を計算し直します。
- 払い過ぎていれば年末の給与で還付(税金が戻ってくる)、足りなければ追徴(追加で納税)されます。
そのため、年末調整は「お金が戻ってくるチャンス」でもあり、「税金を払い過ぎないための大切な手続き」です。
年末調整で必要(提出)な主な書類
年末調整の「書き方」を理解するには、まずどんな書類が登場するのかを知っておくとスムーズです。主な書類は次のとおりです。
※1~4は同じ申込書でお手続きできます。
1.給与所得者の基礎控除申込書
申告する給与所得者の所得金額から基礎控除を算出する申告書です。収入金額と給与所得控除を差し引いた所得金額を記入しましょう。
2025年から基礎控除・給与所得控除の引き上げになっています。
【関連記事】2025年改正、所得控除の種類と条件を理解して節税
2.給与所得者の配偶者控除等申込書
納税者に控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。年間の合計所得金額が58万円以下(給与所得のみ場合は年収123万円以下)、青色・白色事業専従者でない要件があります。
納税者の配偶者に合計所得金額が58万円(給与所得のみ場合は年収123万円以下)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、納税者と配偶者の合計所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
3.給与所得者の特定親族特別控除申告書
これまでは扶養控除は年収一定金額を超えると、納税者は63万円の控除を受けられませんでした。
2025年改正により、納税者に控除対象扶養親族(その年12月31日時点年齢16歳以上)となる人がいる場合には、年収188万円を超えるまでは一定金額を控除できます。
4.所得金額調整控除申告書
所得金額調整控除は次のパターンがあります。給与等が850万円超で子ども(23歳未満)の扶養がいる人or特別障害者の本人or扶養親族や同一生計配偶者がいる人が該当になります。
5.保険料控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書)
生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などを申告する書類です。
関連する会社などから送られてくる「控除証明書」、を見ながら記入します。
6.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年の年末調整のタイミングで「来年分 扶養控除等申告書」も一緒に提出させるという運用をしています。
扶養控除等申告書は、“来年1月以降にもらうお給料の税金を計算するため”の書類なので、年末に“翌年分”として提出するという形です。
7.住宅借入金当特別控除申告書(該当者のみ)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の2年目以降は年末調整で手続きします。税務署から届く「住宅ローン控除の計算明細書」などをもとに記入します。
年末調整の書き方・入力のポイント
ここからは「年末調整の書き方」のポイントを押さえながら、ステップ形式で解説します。
ステップ1:今年の働き方・家族構成を整理する
本人や家族の働き方を整理しましょう。
- 今年の勤務先は?(転職・ダブルワークの有無)
- 一緒に暮らしている家族の人数・年齢
- 今年途中での結婚・出産・離婚・家族の就職/退職はあったか
- パート・アルバイトの家族の年収見込み
この情報が、扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書の記入に直結します。
ステップ2:必要な控除証明書・書類を集める
次に、「年末調整必要書類」を確認しておきましょう。
- 生命保険・医療保険などの保険料控除証明書
- 地震保険料控除の証明書(加入している場合)
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の小規模企業共済等掛金控除証明書
- ご家族の国民年金や国民健康保険を自身で払った場合の領収書や控え
- 住宅ローン控除の残高証明書(2年目以降の方)
これらが手元に揃っていると、保険料控除申告書が記入できます。
ステップ3:扶養控除等申告書を記入・入力する
扶養控除等申告書では主に次の点を確認します。
- 本人(給与をもらう人)の氏名・住所・マイナンバー
- 配偶者や扶養親族の氏名・生年月日・所得見込み
- 障害者・寡婦(夫)・ひとり親など、該当する区分の有無
ポイント
- 扶養家族の所得が増えて控除の対象外になるケース(パート収入の増加など)は見落としやすいポイントです。
- 「前年と同じでいいか」ではなく、その年の状況に合わせて毎年見直すことが大切です。
ステップ4:保険料控除申告書を記入・入力する
保険料控除申告書の書き方が年末調整で最もつまずきやすい部分です。
- 生命保険料控除:
- 一般生命保険料
- 個人年金保険料
- 介護医療保険料
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除(国民年金など自身で払った分)
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・中小企業倒産防止共済など)
ポイント
- 生命保険料控除や地震保険料控除には上限額があるので、申告書の計算式に沿って控除額を計算します。
- 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除は、支払額=控除額になるため、支払った金額をそのまま記入しましょう。
最近は、会社の年末調整ソフトやWeb画面で入力する方式も増えています。この場合も、入力項目自体は紙の申告書とほぼ同じです。国税庁でも年末調整手続の電子化や年調ソフトの案内を行っています。
ステップ5:入力・記入内容を最終チェックする
最後に次の点をチェックしましょう。
- 氏名・住所・マイナンバーは正しいか
- 配偶者・扶養親族の氏名・生年月日・所得見込みに誤りはないか
- 控除証明書に記載されている保険会社名・契約者・支払保険料を正しく写しているか
- 転職している場合、前職の源泉徴収票を提出したか
就業先やソフトによって細かな画面は異なりますが、基本のチェックポイントは共通です。
最終チェックが終わりましたらお勤め先指定の方法で提出しましょう。
FP視点での賢い年末調整
年末調整は単なる事務手続きではなく、家計とライフプランを見直すタイミングにもなります。
- 生命保険料は高額ではないか
- 夫婦の働き方や可処分所得(税と社会保険料を差し引いた所得金額)はいくらか
- iDeCoや小規模企業共済など、節税と資産形成を組み合わせる制度を活用できているか
- 子どもたちや親世代の年収はどうなのか、税の扶養は可能なのか
年末調整の記入だけでなく「ご家庭全体の資産設計の中で、どの控除をどう活かすのがベストか」という視点で考えることが大切です。
また、年末調整で申告を忘れてしまった場合は、申告時期の5年以内に「還付申告」を行い、払い過ぎた税金を還付してもらうことができます。
PrivateFpは数多くのファイナンシャル・プランニングの経験から、ご家族に合ったファイナンシャル・プランを提案します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
【関連記事】2025年最新、健康保険法上と所得税法上の扶養の違いや所得の目安
Q&A よくある質問
-
年末調整と確定申告の違いは何ですか?
-
年末調整は、会社員や公務員などの給与所得者が、勤務先を通じて行う手続きです。一方、確定申告は給与の収入金額が2,000万円を超える方、給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方などです。
-
生命保険料控除証明書をなくしてしまいました。
-
多くの保険会社で、再発行やWeb上での再発行(PDFダウンロード)に対応しています。できない場合は再発行を依頼しましょう。
-
会社でパソコンまたはスマホ入力する形ですが、今までと変わりませんか?
-
紙からパソコン入力に変わっても、聞かれている内容自体は大きく変わりません。本記事を確認して入国しましょう。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
公式サイト iDeCoホームページ
公式サイト 国税庁ホームページ 年末調整がよくわかるページ
お問い合わせ
LINE相談受付中
↓FPおすすめ広告↓
↓FPおすすめ広告↓