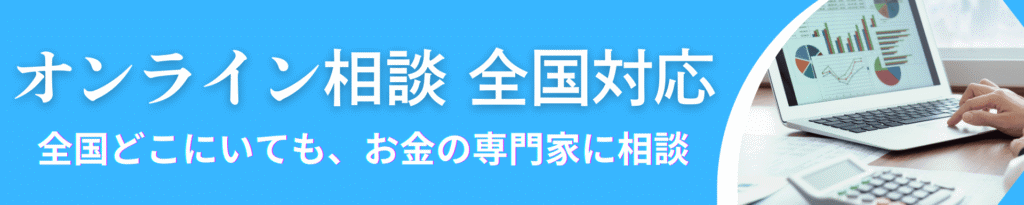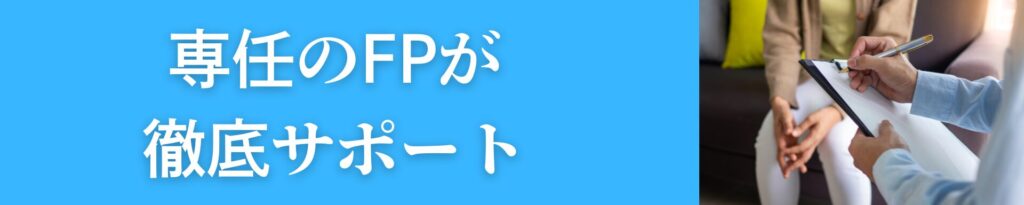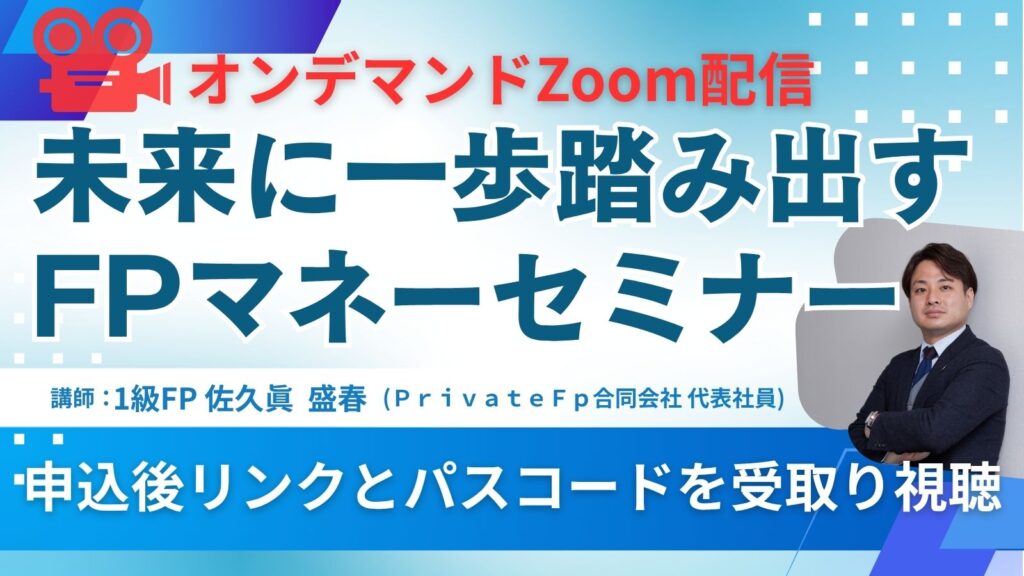【1級FP監修】住宅ローンの家計に合う選び方を解説、変動・固定どれがいい?

お金を借りるということは「将来の収入の先取り」になります。借りる時は慎重に検討することが必要ですが、一般的に住宅のような高額のモノはお金貯めて購入すると必要な時期がずれてしまいます。
その際に利用するのが「住宅ローン」です。今回は住宅ローンの金利の選ぶ際のポイントを確認していきましょう。
目次
【結論】金利上昇に対応できる家計は変動金利、対応が難しい家計は固定金利を選択することも検討しましょう。
金利の種類
住宅ローンの金利は3つの種類があります。
「固定金利」は、完済まで金利が変わらないため、 返済計画が立てやすい点が特徴です。住宅ローンを利用する方の1割が選んでいます。長期金利を基準としています。
金融機関などで低金利の競争が激化している「変動金利型」は、市場金利によって金利が見直されるため、金利上昇時のリスクを考える必要があります。住宅ローンを利用する方の7割が選んでいます。短期プライムレートを基準としています。
この二つがミックスされた「固定金利期間選択型」は、選択した年数(3.5.7年など)が固定金利となり、 固定金利期間終了後は「固定金利期間選択型」か「変動金利型」を選択できます。住宅ローンを利用する2割が選んでいます。
【関連記事】住宅ローンの金利タイプの選び方と審査項目のポイント
返済方式
返済方式は2つあります。
「元金均等方式」の場合、最初は返済負担が大きいですが、毎月の返済額が低減(減少)していきます。
「元利均等方式」の場合、毎月の返済額が変わらず、最初は利子を中心に返すことになり、元本はあまり減らない。
利子負担総額が少ないのは「元金均等方式」です。
住宅ローンの今後、、、安全な返済比率
低金利だった日本でも「金利のある世界」が現実になってきました。日銀のマイナス金利の解除や長短金利操作(イールドカーブコントロール)の修正などが金利上昇の要因です。
今後の金利上昇により、変動金利を選んでいる方の利子負担増の可能性があります。住宅ローン金利を変動金利を選ぶ方が7割を占めるスウェーデンは金利上昇により、住宅を手放す債務者が増加しました。
住宅を購入する際は家計に合った住宅ローンの金利が選びが重要です。
一般的に、今後の金利上昇リスクを許容できない場合は固定金利を選ぶ方が最良と考えます。
また、最近では住宅価格の高騰により、35年ローンでは毎月の返済額が厳しい場合は40年以上の超長期の住宅ローンも選択可能です。
安全な返済比率の目安は、可処分所得の20~25%程度に返済額を設定すると良いです。
人生の3大支出のバランス考える
人生の中では、就職や結婚、車の購入、子ども・孫の教育、住宅購入、リフォーム、老後の生活資金など、さまざまなイベントが発生し、その時々でお金が掛かるものです。
特に人生の3大支出「教育資金」「住宅資金」「老後資金」は特に大きな金額が必要です。
3つのバランスが家計と合っていないと、最後は老後にマイナスが増え、破産になる可能性があります。住宅購入の際に、残りの教育資金や老後資金を考慮して、住宅購入の予算金額を検討しましょう。
PrivateFpはファイナンシャルプランニングを通して、あなたの家計に合った住宅ローン選びを応援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
Q&A よくある質問
-
借入額の目安は?
-
可処分月収の25%以内の返済で逆算し、金利+1.5%のストレスでも返済比率が30%を超えない範囲を上限にしましょう。
-
変動か固定かどっち?
-
家計の耐性で選びます。教育費が重なる世帯、単収入世帯や賃上げが見込めない世帯は固定寄り、二馬力&余力が大きいなら変動寄りの選択で良いです。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
公式サイト 日本銀行ホームページ 長・短期プライムレートの推移
お問い合わせ
LINE相談受付中
↓FP商品広告↓
FP節約できる広告