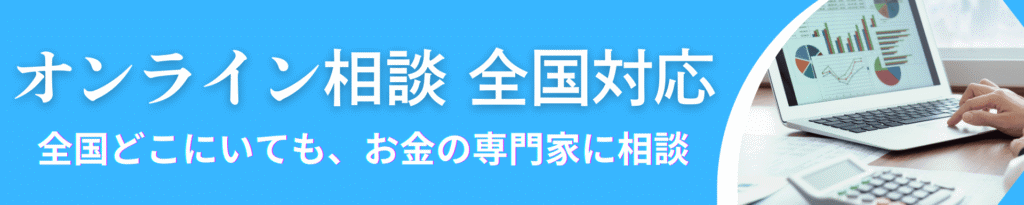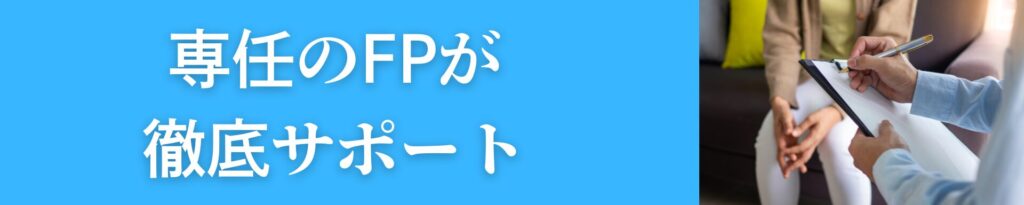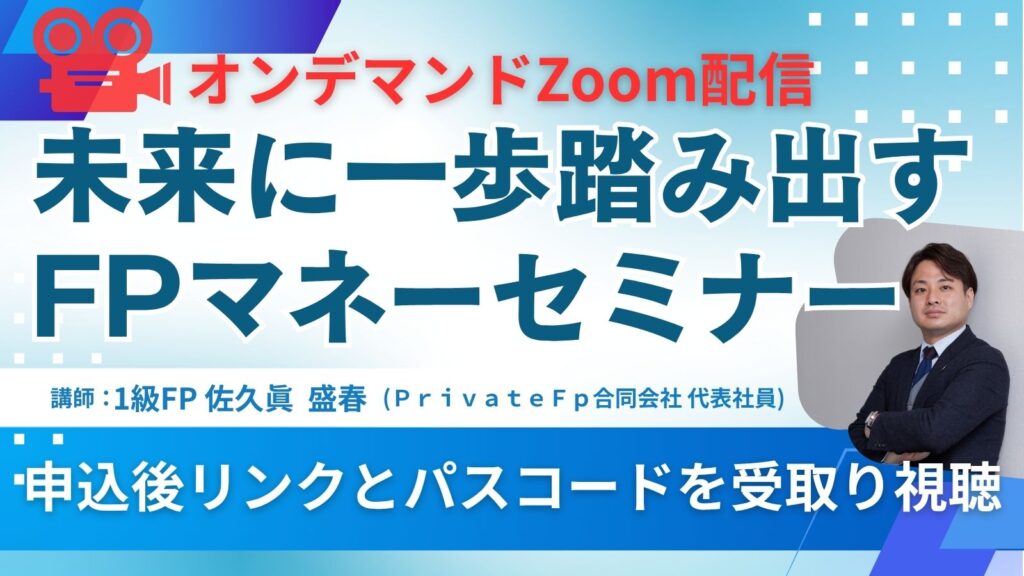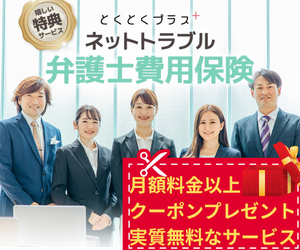【1級FP監修】離婚した時の年金分割制度の流れ、年金記録の按分

年金分割制度とは、夫婦が離婚した時に、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録(厚生年金保険の報酬比例部分)を分割できる制度です。
例えば、夫婦とは婚姻期間中はお互いが協力しながら生活を営んでいますが、離婚すると、厚生年金保険料を納めていた夫だけが、納付した厚生年金保険料により計算された年金を受け取るという問題がありました。
本来なら、夫婦の経済活動には妻の支えも考慮すべきということから、今回は離婚時の2つの年金制度をご紹介します。
目次
【結論】3号分割は単独請求が可能、年金分割制度は離婚等をした翌日から起算して2年以内の請求期限あります。
離婚時の合意分割制度・・・合意必要
2007年4月1日以降の離婚を対象に、婚姻期間中(2007年4月以前も含む)の夫婦の厚生年金保険料納付記録を当事者間の協議で2分の1を上限に分割する制度です。
当事者間の協議で合意を得られない場合には、当事者の一方の請求により裁判所が分割割合を処分することができるようになっています。
当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報「情報通知書」が必要です。
離婚時の3号分割制度・・・単独可能
国民年金の3号被保険者(サラリーマン等の配偶者)と2号被保険者(サラリーマン等)との離婚の場合に3号被保険者からの請求があれば、3号被保険者期間であった期間に係る2号被保険者の年金記録を自動的に2分の1に分割することができる制度です。
2008年4月1日以降の3号被保険者期間が対象になっており、3号分割請求は相手方の合意を要しないため単独で請求できます。
手続きの流れ
①情報提供請求(情報通知書の入手)
年金事務所へ「年金分割のための情報提供請求」を出して、情報通知書を取得しましょう。
②合意分割の合意/調停 or 3号分割
夫婦の合意 or 家裁の調停/審判等で按分割合(上限50%)を決定しましょう。
③標準報酬改定請求(提出)」
決定した按分割合を記入、年金事務所に提出します。
相談先と注意点
離婚後の年金分割の相談、申請先はお近くの年金事務所になります。混雑の防止や円滑な相談を行うために事前予約をできる場合もあります。
注意点は、年金事務者は手続きを行う機関のため、どの按分割合が妥当なのかという相談には答えられません。
また年金分割制度には離婚等をした翌日から起算して2年以内の請求期限があります。また、分割制度でもらった厚生年金被保険者期間は「みなし被保険者期間」として、自分で働いて納付した被保険者期間と違い、老齢年金の受給資格期間(10年)、特別支給の老齢厚生年金の要件(1年以上)等の被保険者期間に算出されないので、自分自身での厚生年金等の加入、納付で受給資格を取得する必要があります。
別れた理由はいろいろありますが、もし当事者一方が知らなければ今までの感謝を込めて教えてあげる配慮も必要だと思います。
PrivateFpは数多くのファイナンシャルプランの経験から、今後の自分自身に合ったライフプランを支援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
Q&A よくある質問
-
情報通知書の取り方は?必要書類は?
-
基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類(マイナンバーカード)、婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)を準備、当事者双方または一方からの請求により可能です。お近くの年金事務所および街角の年金相談センターが窓口です。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
公式サイト 日本年金機構HP 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)
お問い合わせ
LINE相談受付中
↓FPおすすめ広告↓
↓FPおすすめ広告↓